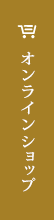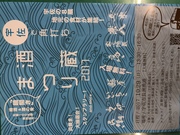 大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130
大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130
10月29(日)に宇佐市で「酒蔵まつり2017」という
イベントが開催されます(^^)
宇佐市の酒蔵8蔵が参加予定です(^^)
もちろん縣屋酒造と大分銘醸も参加します。
本格焼酎をはじめ、日本酒やリキュール等揃えています。
時間は13:30〜16:30を予定しております。
場所は宇佐長洲漁港で
最寄りの駅柳ヶ浦駅から無料のシャトルバスで
行くこともできます。
時間は5分程度で着きます。
鏡割りをするようで、
先着100名様には樽酒と酒の肴を差し上げます(^^)
スタンプラリーや抽選会も行う予定です(^^)
入場は無料です。
参加方法は受付で11枚綴りのチケット¥1,000で販売しています。
チケット1枚では日本酒の普通酒クラス/焼酎
チケット2枚では日本酒の吟醸酒クラス/焼酎/リキュール
という具合で各蔵のお酒を飲むことができます(^^)
飲食ブースは現金払いになります。
興味ある方は是非お越しください!
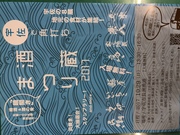 大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130
大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130
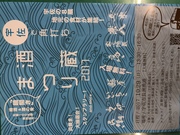 大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130
大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵
縣屋酒造(株)
大分県宇佐市安心院町折敷田130